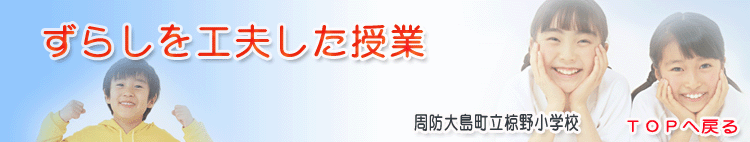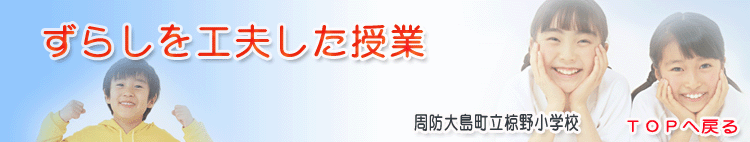| ① |
表1は、一般的なずらしのパターンである。
教師のわたりは、学習活動ごとに両学年を行き来する形をとっている。
問題把握の学習活動と課題追究した後の解決(発表)の学習活動に教師が立ち会えるようにずらしを工夫してある。 |
表1 |
| 5年生 |
6年生 |
| 問題把握 |
|
|
適用・発展 |
| 課題追求 |
|
|
問題把握 |
| 解決・定着 |
|
|
課題追求 |
| 適用・発展 |
|
|
解決・定着 |
|
|
| ② |
表2は、両学年同じ流れの展開例である。
学習内容が多い単元や課題追究にたくさんの活動時間をとりたい授業の場合に有効である。
学習活動をずらすのではなく、両学年ともに問題把握から始めている。 |
表2 |
| 5年生 |
6年生 |
| 問題把握 |
|
|
問題把握 |
| 課題追求 |
|
|
課題追求 |
| 解決・定着 |
|
|
解決・定着 |
| 適用・発展 |
|
|
適用・発展 |
|
|
| ③ |
表3は、片方の学年には最初に指示を与えるのみで、その後は直接指導を行わない展開例である。
教師が児童とともに操作活動を行う場合や細かな指示を出しながら授業を進めなければならない場合に実施するとよい。
片方の学年が課題追究に時間を要する場合や評価テスト(同じ教科にかかわらず)を行っている場合などに実施できる。 |
表3 |
| 5年生 |
6年生 |
| 問題把握 |
|
|
課題設定 |
| 課題追求 |
|
|
課題追求 |
| 解決・定着 |
|
|
| 適用・発展 |
|
|
|
|
| ④ |
表4は、両学年の指導に軽重をつけた展開例である。
複式指導を始めた当初から1単位時間を均等に分けて両学年の指導にあたらなければならないと考えていたが、先進校の先生から学
習内容によっては直接指導に軽重をつけるのも有効だと教わりその後実施するようになった。 |
表4 |
| 5年生 |
6年生 |
| 問題把握 |
|
|
適用・発展 |
| 課題追求 |
|
|
問題把握 |
| 解決・定着 |
|
|
課題追求 |
| 適用・発展 |
|
|
解決・定着 |
|
|
| ⑤ |
表5は、教師が両学年を行ったり来たりする展開例である。
児童にとって本時の学習の流れが明確に理解できている場合や学習ガイドの誘導で授業が展開できる場合に実施できる。 |
表5 |
| 5年生 |
6年生 |
| 問題把握 |
|
|
問題把握 |
| 課題追求 |
|
|
課題追求 |
| 解決・定着 |
|
|
解決・定着 |
| 適用・発展 |
|
|
適用・発展 |
|